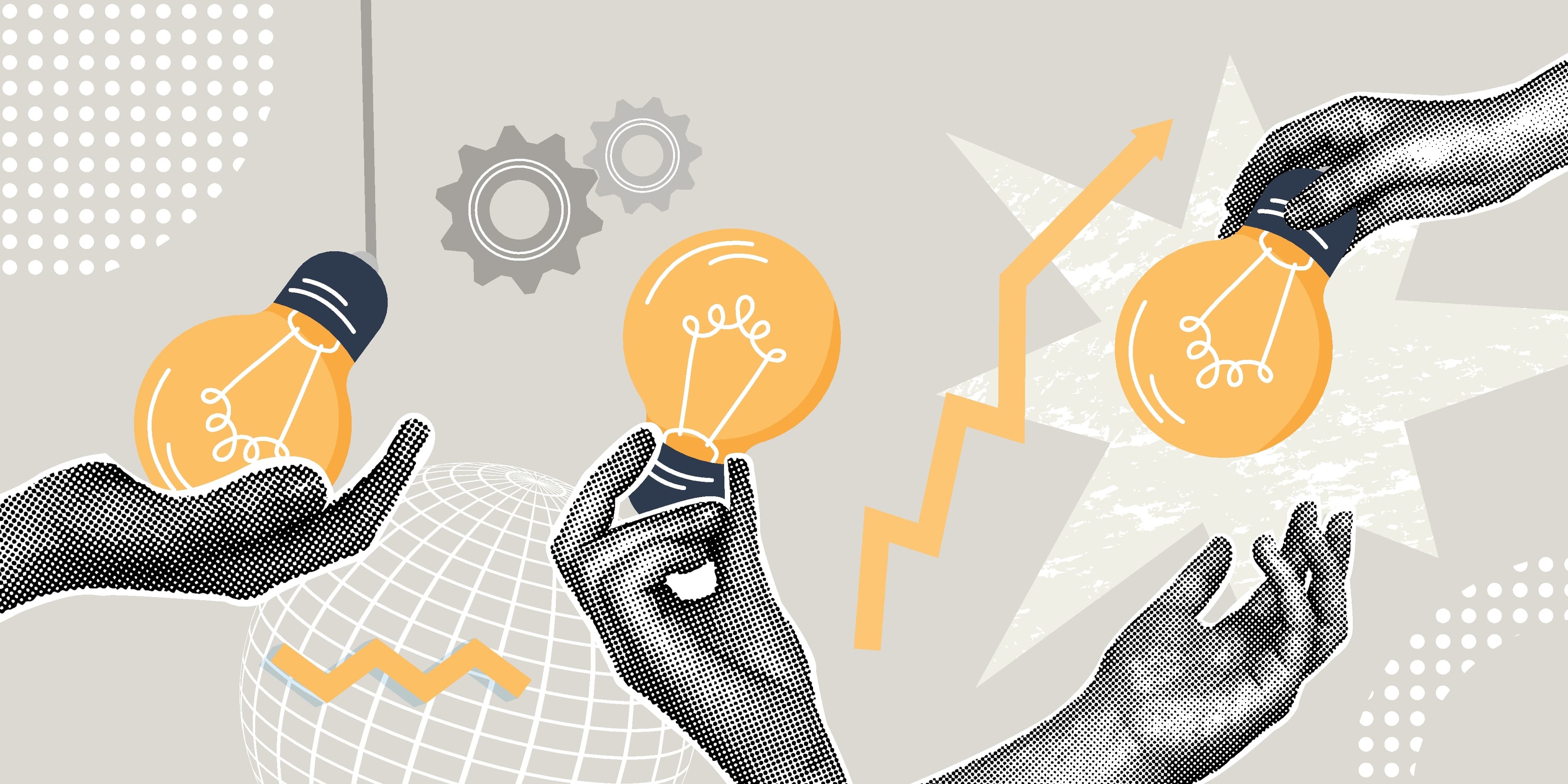なぜ、既存の調査はイノベーションの可能性を見抜けないのか?
近年、日本企業がイノベーションを起こし、新たな市場を創造する上での最大の障壁の一つが、顧客からのネガティブな意見を過度に恐れ、完璧を追求しすぎることだと言われています。つまり、挑戦をすること自体を躊躇してしまい、リスクを取れない状態であるとも言えるでしょう。
従来のコンセプトやデザインの調査では、「好意度」や「購入意向度」といった直接的な評価が中心です。そのため、新奇性の高いコンセプトは価値が直感的に理解されにくく、本来持つポテンシャルよりも低く評価されてしまう傾向があります。
「生活者のネガティブな評価に引っ張られて、新商品開発の社内意思決定ができなかった」「調査では高評価だったのに、市場では全く結果が出ずに廃れていった」
――多くのビジネスリーダーやマーケッターがこうした課題に直面しています。
経験則や肌感覚といった属人的な勘やセンスに頼らず、「イノベーションが受け入れられる範囲」を客観的な指標で捉えることはできないのでしょうか。
本記事では、この問いに答えるべく、当社顧問である柳澤秀吉氏(東京大学教授)を迎え、「覚醒ポテンシャル理論」をテーマにNEW STANDARDの久志尚太郎、関根千恵を交えた鼎談をお届けします。
【鼎談 参加者】

覚醒ポテンシャル理論とは
「覚醒ポテンシャル理論(*1)」は、感性設計学の第一人者である柳澤秀吉教授が研究する「適度な覚醒度が快感情を最大化する」という理論です。
人は、これまで見たことや経験のないもの、複雑なものに直面したとき、脳がフル稼働して情報処理を試みるため「覚醒度」が高まります。一方、見慣れたものや単純なものに対しては、脳の活動が抑えられ、覚醒度は低くなります。
この理論は、コンセプトやデザインが持つ「覚醒度」と、それが引き起こす「感情価(快・不快)」を2軸で分析することで、その潜在的なポテンシャルを客観的に測定します。これにより、従来の評価軸では見抜けなかった中長期的に受け入れられる可能性を秘めたコンセプトを正しく評価することが可能になります。特に、従来の評価軸では見抜けない「新しすぎるゆえに混乱や不快感を引き起こすものの、中長期的には愛着へと変わる可能性を秘めたコンセプト」を正しく評価できる点が優れています。
また、この理論は脳の情報処理の観点に立っており、覚醒度を「驚き(サプライズ)」、好奇心を「情報獲得」とモデル化することで、人間の探求活動や創造的な活動を科学的に説明できる点も特長です。これにより、属人的な勘やセンスに頼らない意思決定が可能になります(*2)。
*1 出典:Berlyne, D. E. 1970. Percept. Psychophys.
*2 出典:Yanagisawa, H. et al. 2019. Front. Comput. Neurosci. Yanagisawa, H. 2021. Front. Comput. Neurosci. Yanagisawa, H. et al. Neural Netw. 2023. Yanagisawa, H. et al. Front. Psychol. 2025.

図1:出典:Yanagisawa, H. 2021. Front. Comput. Neurosci.
(c) Hideyoshi Yanagisawa, The University of Tokyo

図2:東京大学工学系研究科柳澤秀吉研究室とNEW STANDARD社が共同研究開発した「コンセプト・デザイン検証のための定性・定量調査」より引用
(c) NEW STANDARD
イノベーションが受容されるタイムスケール(時間軸)の正体
久志:さて、最初のテーマは、イノベーションが市場に受容されるまでの時間軸についてです。ビジネスにおいて、最適な市場投入のタイミングを見極め、時流の変遷を読み解き、未来を予測する先見性を持つことは、常に重要でありながらその不確実性ゆえに極めて難しい課題となります。
関根:そうですね。例えば、iPhoneやミャクミャク、ポカリスエットといった事例を見ても、イノベーションが世の中に受容され、波及するまでの「潮目」を捉えるのは非常に難しいと感じています。
久志:先生は、このイノベーションが受容されるタイムスケールについて、どのようにお考えでしょうか。
柳澤:これは非常に難しいご質問ですね(笑)。ギリシャ神話では、「クロノス」と「カイロス」という2つの時間があるとされています。クロノスが客観的な物理時間であるのに対し、カイロスは人にとって意味のある主観的な時間です。私たちの記憶に残るエピソードは、この「カイロス的な時間」として刻印されます。
例えば、スマートフォンの事例で言うと、日本や米国のある企業が過去にフルタッチパネルの携帯電話を試み、失敗していたという背景があります。この失敗が人々の記憶に残っていたからこそ、その後のデバイスが登場した際に「完全に新しいもの」としてではなく、「懐かしいけど新しい」という感覚で受け入れられる場合もあるかもしれません。
久志:先生のおっしゃる「懐かしいけど新しい」という感覚は、ユーザー自身の「見てきたことや経験」に紐づき、情報獲得を容易にするということですよね。奇抜すぎるものは情報として受け入れられませんが、ユーザーが観測できる要素があることで、新しい概念も自分ごととして捉えられる。これは、イノベーションを起こす上で非常に重要な視点だと感じました。
柳澤:そうですね。時間も一直線ではなく、時代が繰り返す「振動」として捉えることもできるかもしれません。過去の歴史を紐解くことで、今がその波のどこに位置しているのか、次にどのような文脈に向かっていくのかが見えてくる。この温故知新は、未来を予測する上で強力な手がかりになると思います。

「慣れ」を「愛着」に変えるメカニズム
久志:次に、「飽き」と「愛着」のメカニズムについてお伺いします。発売初期の評価だけでなく、時間経過とともに生じる「飽き」や「慣れ」をどのように捉え、いかに「愛着」へと深化させていくのでしょうか?
関根:ブランド開発や商品開発の現場では、まさにこの「飽き」と「愛着」のバランスが常に課題となります。発売当初は話題になっても、生活者に深く根ざした習慣や愛着へと深化しないケースも少なくありません。長く愛されるブランドや商品を育てるためには、このメカニズムの理解が不可欠だと感じています。
柳澤:どんなに新しいものでも、繰り返されると「慣れ(ハビチュエーション)」が生じます。これはポジティブでもネガティブでもない、ニュートラルな心理現象です。慣れた後に「飽き」につながるのか、「愛着」につながるのか、その分岐点には「能動性」が関わっているというのが私の仮説です。
受け身で触れるだけの刺激は飽きやすいですが、そこに能動的に関わる要素があると、その刺激は「自分ごと化」されていきます。例えば、自分で家具を組み立てることで愛着が湧く「DIY」が典型的な例です。主体的に関わることで、その経験が主観的な時間として記憶され、一種のナラティブ(語り)となって自分の一部になる。これが愛着形成のメカニズムだと考えています。
久志:まさに、企業でビジョンやミッションを策定する際に、社員を巻き込んで一緒に創っていくことが重要だと言われることと通じますね。会社から与えられる受動的なものではなく、自分たちが関わって創り上げた能動的なものとして捉えることで、エンゲージメントが高まる。若年層に流行するカスタマイズ性の高い商品トレンドも、この「能動性」が愛着を高める鍵になっているのだと思います。

「賛否両論」をビジネスチャンスに変えるには
久志:賛否両論を巻き起こす革新的なコンセプトの潜在的なポテンシャルを、どのように見抜くことができるのでしょうか。
柳澤先生:潜在的なポテンシャルを見抜くには、人間の「好奇心」が重要な要素となります。また、表面上は異なる現象であっても、その根底にある「本質」をいかに見抜くかという思考の訓練も不可欠です。
私の研究室では、ロボットからデザイン、食品まで多岐にわたる研究をしていますが、その本質の部分には共通性があります。深く掘り下げていくと、表面的には多様に見えるものが、実は深いところで繋がっている。哲学や歴史を学び、あるいはAIも交えて多様な人々と議論を交わすことで、そうした本質を見出すことができると考えています。
関根:人々が過去にどんな「好奇心」を抱き、何を求めて行動してきたのか。そういった人間の根源的な好奇心や欲求の変遷、つまり時代の大きなうねり(トレンドサイクル)を仮説として持つことが、表面的な「賛否両論」に惑わされず、潜在的なポテンシャルを見抜く上で重要だと改めて認識しました。この仮説を、覚醒ポテンシャルのような科学的な理論に基づいた評価方法を活用することで、より確かなものにできると思いました。
久志:表面的な事象の奥にある「本質を見抜く思考」の重要性、大変勉強になります。イノベーションを成功させる上で、多様な事象からその本質を見出す能力は不可欠だと改めて感じました。特に、革新的なコンセプトが故に「賛否両論」に直面するビジネスの現場では、初期の批判的な声に過剰に反応することなく、この本質を見極める力が求められます。この思考こそが、真の潜在的ポテンシャルを評価するための指針となるだけでなく、多くの人が批判や混乱に目を奪われる中で、そのコンセプトが持つ将来的な価値や市場機会をいち早く認識し、競合に先んじて機会を掴むための重要な戦略となり得ると感じました。まさに、この潜在的ポテンシャルを見抜く戦略的判断こそが、その後のビジネスチャンスを現実のものとするための出発点となるのではないでしょうか。
覚醒ポテンシャルで切り拓く、日本企業の未来
関根:覚醒ポテンシャル理論は、イノベーションにおける3つの難題「時間軸」「飽きと愛着」「賛否両論」に対し、新たな視点と客観的な指針を提供できる可能性を強く感じました。
久志:属人的な勘やセンスに頼るだけでなく、科学的な理論に基づいた評価や意思決定が、日本企業の挑戦を後押しし、新たな未来を切り拓く鍵となるかもしれません。
本日は貴重なお話をありがとうございました!